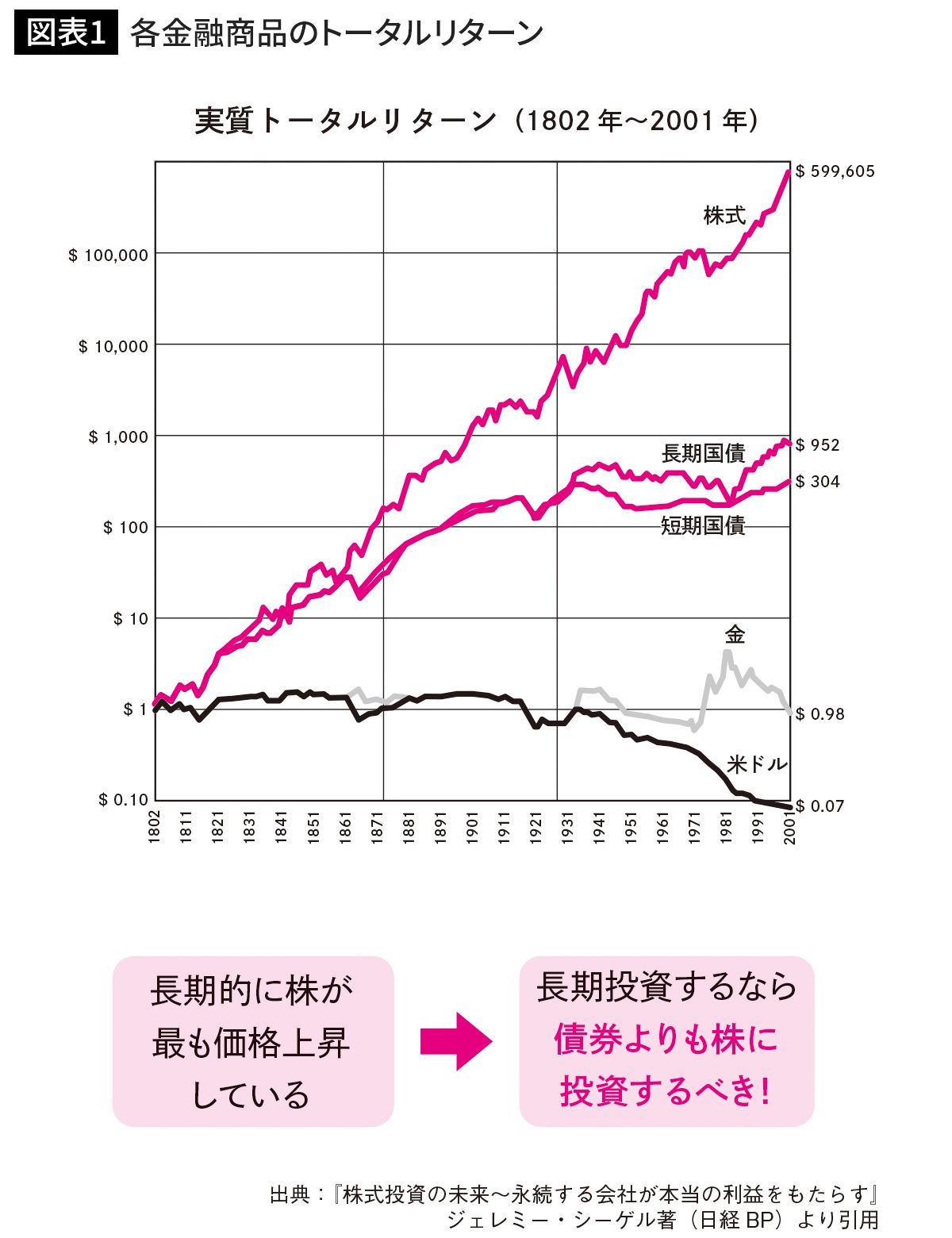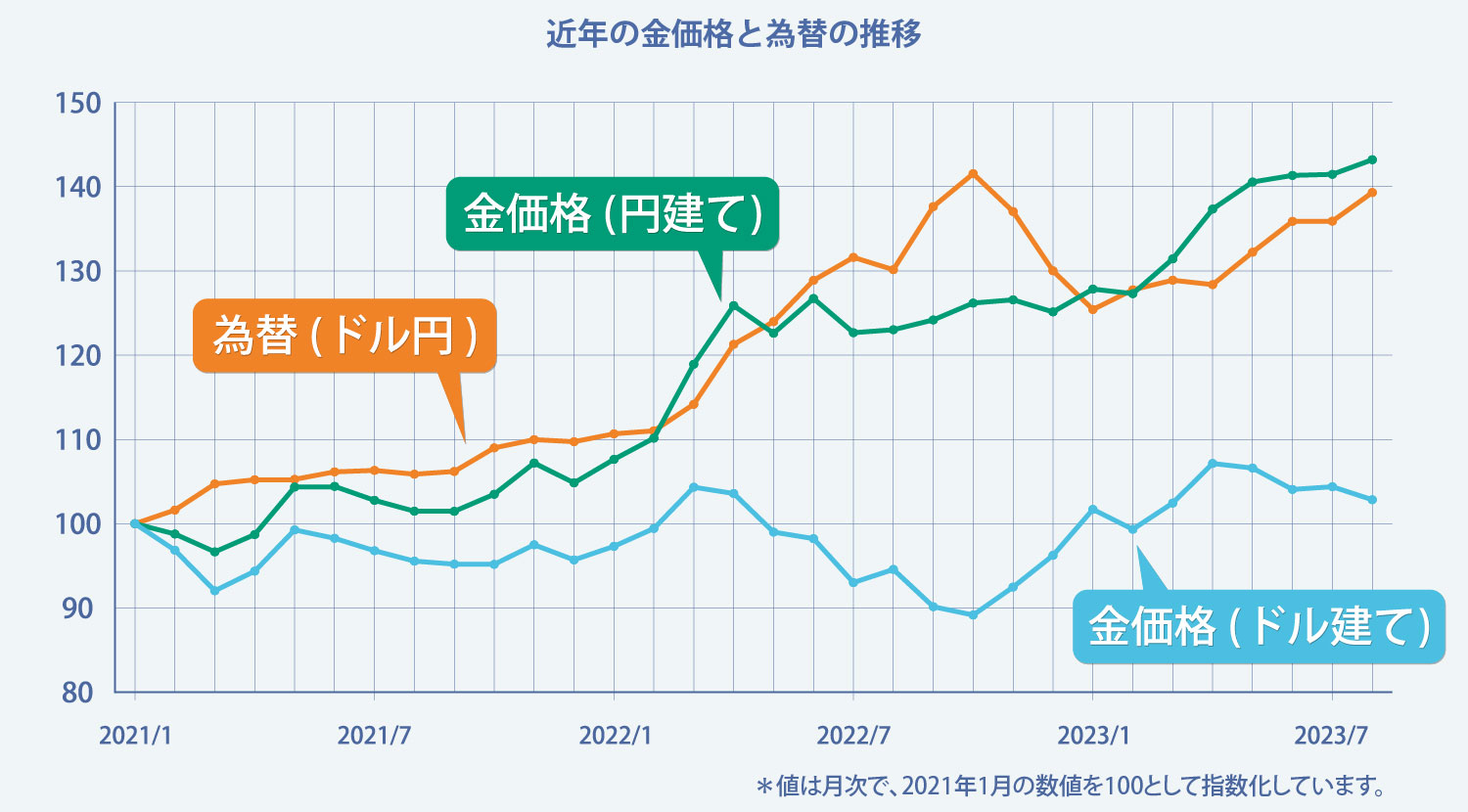おれは以前から大いに疑っている。「日本国民はウクライナにとても同情的で、ロシアの侵略の被害者とみなしている。ホワイトハウスでゼレンスキーが叱責されるこの映像が日本のテレビで放映されれば、アメリカは本当に日本を守ってくれるのか疑問を抱く人が増えるだろう」 https://t.co/yPzBGqQRt8
— 町山智浩 (@TomoMachi) March 1, 2025
もし、日本に有事が起きて、たとえば尖閣諸島が占領された場合、トランプなら同じこと言うでしょうね
— やす 🇺🇸 ベンチャーキャピタル (@YasLovesTech) February 28, 2025
「尖閣は諦めろ。和平しろ、沖縄までとられたいのか?」
と。攻められたらほんと終わり。
そうならないよう抑止力は高めることは本当に重要 https://t.co/VcDwA6EhH8
もし、日本に有事が起きて、たとえば尖閣諸島が占領された場合、トランプなら同じこと言うでしょうねだな・・・ただ、トランプじゃなくてもありえるな。
「尖閣は諦めろ。和平しろ、沖縄までとられたいのか?」
と。攻められたらほんと終わり。
そうならないよう抑止力は高めることは本当に重要
憲法違反ではないにせよ、大学も含めて公立無料化を優先すべきだな。それが実現できてから私立にまわせばよい。私学助成ほど明白な憲法違反はないと言われますね。 https://t.co/5lEvyrrei9 pic.twitter.com/MYqt6Ezlp8
— Spica (@CasseCool) February 28, 2025
異なったとしても税率引き下げで「減税」になると限らない法人税と、控除引き上げで必ず「減税」となる所得税では財源論の必要性がまるで異なる。
— Spica (@CasseCool) February 28, 2025
※アイルランドの法人税率と法人税収/GDP比の推移… https://t.co/aM7Ct1YX4x pic.twitter.com/kNOHGQGm7A
私は法人税が40%だった平成元年に生まれました。現在の法人税は23.2%ですが、ここまで減税するのに「財源の提案」が行われていた記憶がありませんまるで問題にしなかったのはたしかにおかしいな。
分かる人にとってはなんで分からないのかが分からない。分からない人にとってはなかなか直感的に納得できない。そんな不思議な問題です
スッとわかるひともいるんだな・・・・おれはいまいち納得していない。
Perplexity
モンティ・ホール問題は、1960年代のアメリカのゲームショー番組「Let's make a deal」に由来する確率論の問題です。この問題は、直感的な判断と数学的な分析の違いを示す興味深い例として知られています。
## 問題の起源と大論争
1990年9月9日、ニュース雑誌「Parade」のコラム「マリリンにおまかせ」で、マリリン・ヴォス・サヴァントがこの問題に対する回答を掲載しました。サヴァントは「ドアを変更すれば、景品を当てる確率が2倍になる」と正しく回答しましたが、これが大論争の引き金となりました[1][2].
この回答に対して、約1万通もの反論の投書が殺到し、その中には1000人近い博士号保持者からのものも含まれていました。多くの反論者は「ドアを変えても確率は2分の1である」と主張しました[2].
## 論争の展開
サヴァントは複数回にわたって説明を試みましたが、反論は収まりませんでした。この問題は単なる数学的議論を超えて、ジェンダー問題にまで発展しました[2].
最終的に、数学者のアンドリュー・ヴァージョニがコンピュータシミュレーションを行い、サヴァントの回答が正しいことを証明しました。その後、カール・セーガンなどの著名人も問題を解説するようになり、徐々に正しい解答が受け入れられていきました[2].
Paul Erdős, one of the most prolific mathematicians in history, remained unconvinced until he was shown a computer simulation demonstrating Savant's predicted result.[6]
なんと数学者も最初は納得しなかったんだ・・・・カッコつけて納得するふりをしてもしょうがないな。
生産性は上がったが、内部留保が増えただけで賃金はあがっていない。
経営者は毎年賃金あげているじゃないか、と思っている。
組合は賃上げより雇用の安定を要求してきた長期雇用にない非正規にいる人は賃金は低く抑えられっぱなし。
と。
間違った人たちが、あのアメリカとヨーロッパの大陸の労働規制の緩和を入れましょうと言っていますが、いやそれはヨーロッパの場合、付加価値の分配がすごく多くて、むしろ生産性に比べると実質賃金が多すぎているから、その結果失業率がすごく高くなっているのです。人件費が高いから人を雇うより機械をもっと導入した方がいいので、失業率が高くなってしまっているから、雇用の流動化を進めた方がいいという話になっています。しかし、日本の場合はむしろ賃金が安すぎるので、企業は喜んで人を雇っているというのが実態ですね。
欧米のまねすりゃいいってもんでもないな。