だからそれは違うんだって。クルーグマンの話は2000年代。
— 池田信夫 (@ikedanob) October 13, 2024
今は日本の労働人口あたり成長率はG7で最低。アベノミクスが勤勉な日本人をだめにしてしまった。 https://t.co/4SfVm0mLKh pic.twitter.com/KxvmqwMjSl
鳩山紀一郎 国民民主党 東京都第2区総支部長 @Hatoyama_Kii これは以前からノーベル賞経済学者のクルーグマン氏も主張していたことで、要するに、日本の現役世代は少子高齢化による負担に頑張って耐えてきたということです。クルーグマン氏が反対していた消費税引き上げを断行して景気悪化を招いたのが野田政権や安倍政権です。非合理的な緊縮財政はダメです。いずれにせよ、消費税あげると景気悪化するんだな。成長率が悪い中やったらなおさらだろうな。
かつて「長期停滞論」でバラマキを推奨していたサマーズも、高圧経済論には反対。
自分
サマーズも、高圧経済論には反対なの?
Perplexity
サマーズの立場は高圧経済論に対して複雑で、時期によって変化しています。## サマーズの見解の変遷**初期の立場**当初、サマーズは「長期停滞論」を唱え、財政政策の活用を支持していました[2]。この考えは高圧経済論と親和性があり、需要刺激によって経済成長を促進する点で共通しています[1][3]。**最近の懸念**しかし、最近ではサマーズはインフレに対する警戒感を強めています[2]。特に、アメリカン・レスキュー・プラン(ARP)の規模が大きすぎることを指摘し、過度の財政刺激がインフレを引き起こす可能性を懸念しています。## サマーズの現在の立場サマーズは完全に高圧経済論に反対しているわけではありませんが、その実施には慎重な姿勢を示しています。1. インフレリスク:大規模な財政刺激がインフレを引き起こす可能性を警告しています[2]。2. 効果の不確実性:「力強い景気拡大自体が潜在成長率を高める」という高圧経済論の前提に対して、その効果が確実ではないと考えています[2]。3. 長期的な影響:短期的な成長率の上昇が必ずしも潜在成長率の向上につながるわけではないという見方を示しています[2]。サマーズの立場は、高圧経済論を完全に否定するものではありませんが、その実施には慎重であるべきだという考えを反映しています。経済政策の効果と潜在的なリスクのバランスを取ることの重要性を強調しているといえるでしょう。Citations:[1] https://www.dlri.co.jp/report/macro/162974.html[2] https://www.tkfd.or.jp/research/detail.php?id=3750[3] https://www.dlri.co.jp/report/macro/247684.html[4] https://mainichi.jp/premier/politics/articles/20210622/pol/00m/010/005000c[5] https://www.boj.or.jp/about/press/koen_2023/ko231202a.htm[6] https://media.rakuten-sec.net/articles/-/7019[7] https://www.mizuho-rt.co.jp/publication/mhri/research/column/executive/pdf/km_c210121.pdf[8] https://www.nikkei.com/article/DGXZQODB22A1Q0S1A320C2000000/
池田信夫 reposted帝国データバンクのカレーライス物価指数。皆さんが大好きな2%インフレが定着した世界ではカレーライスは毎年10%くらい値上がりするでしょう。 pic.twitter.com/YqiMqVY9jl
— Shen (@shenmacro) October 11, 2024
デフレ脱却と物価高対策を同時に進めると、やがて自己矛盾に陥り、自分でも何をやっているのか分からなくなるだろう。 https://t.co/JwADfVbGBk
— 西野智彦 Tomohiko Nishino (@real_tonishino) October 13, 2024
えーと、消費が弱いのはインフレが原因で消費が伸びるにはインフレが収まる必要があり、そうするとデフレ脱却…いかん頭が混乱してきた。?????
パンダは要らんな。パンダは要らない。
— buvery (@buvery2) October 13, 2024
白黒毛並みを剃れば、ブタと変わらないよ。 https://t.co/ZRfdEroSQz
この木下さんという人の文章はたしか読んだことがあるが、薬物使用をしている若者がいることを認識しながら警察に通報せず黙認しているのが本当なら、そりゃまずいだろう。木下氏はクルドに同情的ではあるが、実情の把握はしている。
— buvery (@buvery2) October 13, 2024
クルドかいわいそう難民ヘイト
というNHKを始めとして、一般に流布されている説は全くの誤り。 https://t.co/sfUFeoVe1s
幼稚園はなんて言っているんだ?・・・そこが問題だろうね。川口市内某幼稚園の運動会です。「校庭が狭いので2メートルまでの小型テントと指定されてるのにコイツらだけ「そんなの知るか」と大型タープで我が物顔でした。とにかくルールを守る気はないですね」との日本人父兄の言葉。子供への影響も考えない。親の資格があるのか疑問を持つ人たち pic.twitter.com/RJKMBOSnmM
— 石井孝明(Ishii Takaaki) (@ishiitakaaki) October 13, 2024
金与正氏「必ず恐ろしい惨事が起きる」と報復示唆…平壌に独裁批判ビラ、無人機でまかれる
くちさき女だからな。火の海なったことはないべ?
Kim Yo-jong is all talk."
この図表を毎日2人で見ろや https://t.co/h1sUNcZmJe pic.twitter.com/u9z59VXQE7
— 世代間格差 (@roujin_kansha_) October 12, 2024
図表6-2 「自己負担割合が増えると外来受診が増える」
NBERワーキングペーパーw19726の要約論文タイトル: The Effect of Patient Cost Sharing on Utilization, Health, and Risk Protectionこの論文は、患者の自己負担額が増加した場合、医療の利用や健康状態、そしてリスク保護にどのような影響を与えるのかを、日本のデータを基に分析しています。主な研究結果医療の利用: 自己負担額が増加すると、医療の利用が減少する傾向が見られました。特に、高額な医療サービスの利用が大きく減少しました。健康状態: 医療の利用が減少することで、健康状態が悪化する可能性が懸念されましたが、この論文では、短期的な健康状態への悪影響は限定的であるという結果が得られました。リスク保護: 自己負担額の増加は、経済的に余裕のない人々にとって、医療へのアクセスを制限し、健康リスクへの備えを困難にする可能性があります。
3つの結論に達しました。
まず、70歳時の自己負担額の軽減は、医療の利用を不連続的に増加させます。対応する弾性値は控えめで、外来受診と入院の両方で約-0.2です。利用のパターンをより詳細に調べると、患者の自己負担額の低下は、重篤な診断と非重篤な診断の両方を提示する患者の数の増加と関連していることもわかります。例えば、適切かつ早期の治療により後続の回避可能な入院を減らすことができる、外来受診可能な疾患(ACSC)の診断に対する外来受診の増加が大きく見られました。第2に、メリットの観点から、患者の自己負担額の低下が、死亡率や自己申告による身体的および精神的な健康などの健康指標のいずれかを改善することを発見していません。健康はストックであるため、最も観察可能な健康効果が実現するまでには時間がかかることがあります。したがって、死亡の原因が急性でない限り、RDアプローチを使用してこれを解決することは困難です。それにもかかわらず、急性原因別死亡率でも変化は見られません。利用の変化にもかかわらず、健康状態に違いがないことは、患者の自己負担額が、少なくとも短期的に健康に悪影響を与えることなく、医療の利用を減らすことができることを示唆しています。最後に、70歳時の自己負担額の低下は、特に分布の右端で、自己負担額の減少が利用の増加による相殺効果を上回るため、自己負担額の支出を減らすことがわかります。この結果は、高額な医療費を負担する患者は、自己負担額の低下によるリスクに対する財務的な保護から大きな恩恵を受けることを示唆しています。
これがいろいろ論議を呼んでいるが、終末期医療費は老人医療費の1割ぐらいで、短縮しても大した効果はない。
— 池田信夫 (@ikedanob) October 13, 2024
大部分のコストは長期入院とバカ高い薬にかかっているので、窓口負担を3割にして入院を減らすことが大事。 https://t.co/cuoThyzJJO
大部分のコストは長期入院とバカ高い薬にかかっている
先の論文によると
. For example, I find large increases in outpatient visits for diagnoses that are defined as Ambulatory Care Sensitive Conditions (ACSCs), for which proper and early treatment reduces subsequent avoidable admissions.
例えば、適切で早期の治療がその後の不要な入院を減らすとされる外来診療敏感性疾患(ACSCs)の診断において、大幅な外来受診の増加を確認しています
外来患者数と年齢の相関図

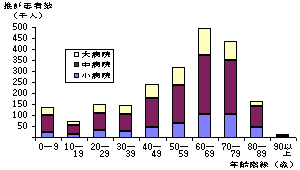




0 件のコメント:
コメントを投稿